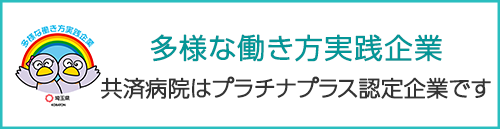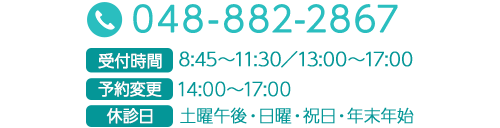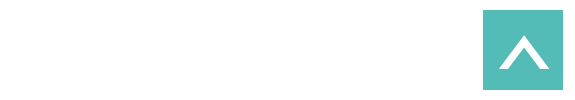検査科紹介

ご挨拶
臨床検査は病気の診断や治療のために必要不可欠です。臨床検査は患者様の血液や尿を扱う「検体検査」と患者様に接して行う心電図や超音波などの「生理機能検査」まで広範囲です。
当院検査科では「正確な検査結果を迅速に提供する」ことを職務とし、休日夜間24時間オンコール体制での緊急検査や輸血にも対応しています。また人間ドックや各種健康診断も行い、現在10人の臨床検査技師で業務を担当しています。
2021年3月(New)超音波装置を最新型に変更しました。
検体検査

血液検査
血液中の白血球や赤血球、血小板の数を測定することで貧血や炎症の程度、出血傾向を判断する検査を行っています。また、形態を顕微鏡で確認しウイルス感染や血液の病気を判断する検査も行っています。
生化学検査
血液を遠心分離して、自動分析機で肝機能検査(AST,ALTなど)、腎機能検査(BUN、CRE、UAなど)、脂質検査(TC、HDL-C、LDL-C、TG)、糖質検査(GLU、HbA1c)、蛋白質(TP、ALB)、電解質検査、感染症検査、凝固検査(PT、APTT、Dダイマー)、BNPなどの測定を行っています。至急検査では30~40分ほどで結果を報告できます。腫瘍マーカーや内分泌検査などは外部に委託しています。
一般検査
尿中の成分(蛋白、糖、潜血など)や細胞、細菌などを検査することで、糖尿病や腎臓病、尿路感染などの様々な病気や病態判断に役立ちます。
迅速検査
5分~20分で結果が分かる迅速検査としてコロナウイルスPCR検査NEAR法、コロナウイルス抗原検査、インフルエンザ検査、妊娠反応検査、真菌(水虫)検査、溶連菌検査、肺炎球菌検査、マイコプラズマ検査、便潜血、便中ピロリ抗原検査、クロストリジウム・ディフシル抗原および毒素検査などを行っています。
輸血検査
安全な輸血を行う為に必要な検査(血液型検査や交差適合試験など)や自己血輸血貯血の介助、輸血用の血液製剤の適正な管理、保管、供給を行っています。さらに、輸血により肝炎ウイルスやエイズウイルスに感染していないかを確認する為の輸血前後の感染症検査も実施しています。
病理・細胞診検査
外部へ委託しています。内視鏡検査で採取された胃や大腸の生検の病理組織診断や手術で摘出された臓器の病理組織診断結果、尿や喀痰、婦人科の細胞診結果は約1週間~10日かかります。
細菌検査
外部へ委託しています。菌の発育状況によって変わりますが結果は約1週間程度かかります。結核菌のような抗酸菌は発育が遅いので最終報告までに約6~8週間かかります。
生理検査

心電図
安静時心電図検査:不整脈や虚血(心臓の血管が細くなったり詰まったりして血液の流れが悪くなること)など心臓に異常がないか調べる検査です。
ホルター心電図【予約制】:動悸・息切れ・胸痛などの症状が病院にいない時に起こる場合に有効です。24時間心電図を記録します。結果は約2週間かかります。
マスター負荷心電図:2段の階段をリズムに合わせて昇降します。運動後1分、3分、5分、7分、10分後の心電図をとり、安静の状態での心電図と比較します。

2021年3月 超音波装置を更新
2024年3月(NEW)最新超音波装置1台増台
日立ARIETTA850SE(現富士フィルム)に買え替えより鮮明な心臓や腹部の画像や観察が可能となり、今まで以上により正確な診断が可能となりました。
また検査の時間短縮にもつながっております。
超音波検査【予約制】
*超音波検査士認定資格取得人数(日本超音波医学会) *消化器領域4名、体表臓器領域1名、健診領域2名
腹 部 :肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を中心に各臓器に病変がないかを調べます。
心 臓 :心臓の動き・大きさ・弁の機能などを調べます。
頚 動 脈 :頚動脈の動脈硬化の程度や狭窄病変、血管の走行異常などを調べます。
乳 腺 :乳腺内の腫瘍性病変の位置や大きさ、性状などを調べます。
甲 状 腺 :甲状腺の大きさ、腫瘍性病変の位置や大きさ、性状などを調べます。
下 肢 静 脈 :下肢の静脈に血栓がないかを調べます。
乳房超音波検査について
音波診断装置で、超音波を乳腺に当て、はね返ってくる反射波をコンピュータが画像化したものです。産婦人科で胎児を見る超音波診断装置と同じなので痛みはありません。乳腺内の腫瘤や乳管拡張などの変化を観察します。問診や視診、触診と合わせて受診してください。
肺機能検査
肺の大きさや気道の異常などの呼吸機能をみる検査です。肺活量、努力性肺活量の検査を行っています。患者様と技師との連携が大切な検査です。
眼底検査
暗い部屋で瞳孔を開かせた状態で眼の奥の血管の状態を見る検査です。瞳孔の開きが悪い方には散瞳薬(目薬)を使用する場合があります。
簡易型無呼吸検査(SAS)【予約制】
睡眠時にいびきのひどい方、呼吸が止まっていると言われている方におすすめの検査です。簡単な器械を持ち帰っていただき就寝時に検査します。結果は約1週間かかります。
聴力検査
両耳にヘッドホンをつけて、低音と高音の音が聞こえるかを検査します。
血圧・脈派検査
血管年齢を調べる検査です。動脈硬化や血管のつまりがわかります。
精度管理体制

内部精度管理
始業前にコントロール血清及びコントロール血球を測定し測定値をチェックしています。
既に値のわかっている血清および血球を測定することで測定機器や測定試薬に異常がなく正しい測定結果が報告されていることを確認するために測定をします。
外部精度管理
日本臨床検査技師会精度管理調査、埼玉県医師会精度管理調査などに毎年参加し、院内のみならず外部の施設と比較しても正しい測定結果が報告されていることを確認しています。
保有機器
- 日立自動分析装置3500(日立)
- 多項目自動血球分析装置(シスメックス)
- 血液分析装置(テクノメディカ)
- 超音波診断装置ARIETTA850SE (富士フィルムヘルスケアシステムズ株式会社)
- 解析付心電計(フクダ電子)3台
- ホルター心電計(フクダ電子)2台
- 血液脈波検査装置(フクダ電子)
- 電子診断用スパイロメータ(フクダ電子)
- 無散瞳眼底カメラ(トプコン)
- オージオメータ(MINATO)
- 携帯用睡眠時無呼吸検査装置(帝人)
- ID NOW INSTRUMENT(Abbott)2台